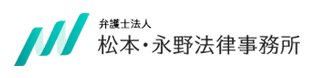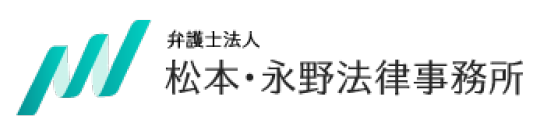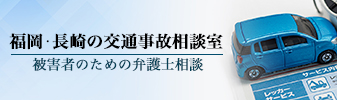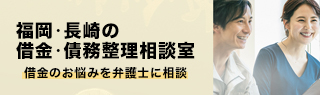遺言書が残されていた場合には、その内容に従って遺産を分割していきます。しかし、遺言書がなかった場合や、相続人が大勢いたり、遺産が多額である場合には、遺産を誰にどう分割するのか、その方法を決める必要があります。
どのような手続きや方法があるのか、さらに争いを防ぐための手順や留意点をご紹介しましょう。
1.遺産分割の手続きについて
遺言書が残されていれば、その内容に従って遺産を分割していきます。しかし、遺言書がない場合には、はじめに相続人全員で(1)遺産分割協議を行い、分割方法を決めていきます。協議をしても合意できなかった場合は、家庭裁判所で(2)遺産分割の調停を行います。それでもまとまらなかった場合は、(3)遺産分割の審判を受けることになります。
(1)遺産分割協議
遺言書が残されていなかったり、遺言書で相続分の指定しかしていない場合や、遺言書に書かれていない財産がある場合などには、相続人間で遺産分割の協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加していないと無効になるので、ご注意ください。
(2)遺産分割の調停
遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。
遺産分割調停では、家事審判官(裁判官)と調停員が相続人の間に入り、話し合いによって分割内容を決めていきます。
調停でもまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きが開始されます。
(3)遺産分割の審判
遺産分割調停が成立しなかった場合は、申し立てをしなくても自動的に審判に移行します。
審判手続きでは、裁判官がさまざまな事情を考えあわせて、審判を下します。審判が出ると、いったん終結しますが、納得がいかない場合は、「即時抗告」という不服申し立ての手続きを行うことが可能です。
即時抗告が認められなかった場合は、許可抗告や特別抗告という手続きもありますが、これらが認められるケースは限られています。
2.遺産分割する4つの方法について
相続財産には、現金や預金以外にも、不動産や貴金属、有価証券など分割が難しいものもあります。
それらを遺産分割する方法は、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割、(4)共有分割の4種類があります。
どの分割方法を選択するかは、当事者の選択か裁判所の裁量によって決まります。
(1)現物分割
現物分割とは、預貯金など現金のみの場合や、不動産や有価証券などを換金せずに、そのまま分割する方法をいいます。
例えば、相続人が3人で相続財産が現金・土地・株式証券があった場合、一人に現金、一人に土地、一人に株式証券という形で分割します。
換金する手間がないので手続きは簡単ですが、相続人の間で取得格差が大きいケースもあります。その場合には、他の分割方法にしたり、併用するほうがスムーズに分割できるでしょう。
(2)代償分割
代償分割とは、相続人の中の一人が法定相続分を超える価値のある相続財産を得た場合に、他の相続人との差を代償金として現金で支払う方法をいいます。
この場合、不動産の評価額や税金の支払いなど、全員が納得できる金額の算出が難しくなるため、争いが起こりやすくなります。
裁判所が代償分割をさせる場合は、現物分割ができないなどの特別な事情があり、代償金を負担する相続人に資力があることが条件となります。
(3)換価分割
換価分割とは、不動産や動産、有価証券などをすべて売却して、その代金を分割する方法をいいます。
現物分割が難しく、財産の取得希望者がいない場合や、資力がなく代償分割ができない場合に用いられます。現金を分割するので平等に分けられますが、売却に時間がかかったり、人が住んでいる土地は借地権の問題が発生する可能性があります。
換価分割には、当事者の合意によって売却する場合と、裁判所の命令により競売にかける場合があります。
(4)共有分割
共有分割とは、相続財産の一部または全部を、相続人が共同で取得する方法をいいます。
共有分割は遺産分割の最後の手段で、上記の(1)(2)(3)のいずれの方法でも分割が困難である場合に限り、用いられます。不動産などの財産を共有にしてしまうと、所有者全員が同意しないと売却することはできません。共有関係を解消するためには、共有物分割訴訟を起こす必要があります。
3.遺産分割を行う手順について
遺産分割を行うために決まった順番はありませんが、一般的に多く行われている流れを追っていくことで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズに遺産分割協議を進めることができます。
(1)遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書の有無を確認しますが、作成された遺言書の種類によって、その方法は異なります。
公証人が関わって作成した「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」は、全国の公証役場にデータベースがあります。公証役場に問い合わせると、遺言書があるかどうかを確認することができます。
「自筆証書遺言」の場合は、被相続人が保管しておきそうな場所を探してみたり、思い当たるふしのある人に訊ねてみるなど、自身でお探しになる必要があります。
遺言書の確認について、詳しくはこちら
(2)相続人を確定する
次は、相続人を確定させます。遺産分割協議を行った後に、相続人が他にもいたことがわかると、協議をやり直さなければなりません。
遺言書が残されていない場合は、「法定相続人」が相続人となります。遺言書がある場合は、遺言によって指定された人が相続人となりますが、法定相続人には遺留分が認められています。
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を集めて、相続人を確定させます。
相続人について、詳しくはこちら
(3)相続財産をすべて確定する
次に、遺産相続の対象となる財産を調べます。不動産・動産などの権利、債権や債務など、プラスはもちろん、マイナスもすべて含めた財産を調べ上げます。相続財産を確定したら、一覧表である財産目録を作成しておくとよいでしょう。
不動産や株式の価格はさまざまな評価方法があり、それによって大きく価格が異なることがあります。そのため、その評価方法に対して相続人全員が理解し、評価額についても合意する必要があります。
相続財産について、詳しくはこちら
(4)遺産分割協議を行う
相続人と相続財産を確定したら、まずは相続人全員で遺産の分割方法について話し合いを行います。
話し合いによってすべての相続人が納得することができたら、遺産分割は解決となります。
相続人の中で、遠方に住んでいたり、疎遠などの理由で協議の参加を渋る方がいる場合は、書面でのやり取りをお願いします。また、調停・審判を申し立てることも考えておくとよいでしょう。
遺産分割協議について、詳しくはこちら
(5)遺産分割協議書を作成する
相続人同士で話し合って合意できた内容は、「遺産分割協議書」として書面で残しておきましょう。必ず作成しなければならないものではありませんが、作成しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、不動産の相続では相続登記の手続きなどで、遺産分割協議書が必ず必要になります。銀行預金の相続手続きにも必要になる場合があるので、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書について、詳しくはこちら
(6)合意できなければ調停・審判を申し立てる
もし遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、民法で定められた法廷相続人の割合をもとに、調停や審判によって判断をします。
遺産相続に関する調停や審判は、ぜひ専門の弁護士におまかせください。公平で納得のいく解決が見つかるよう尽力いたします。
4.遺産分割の再協議ができる場合は?
相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成した以上、協議内容が法的に有効となっているため、基本的には再協議はできません。
しかし、協議後に新たに相続財産が発見されたり、一部の相続人が財産を隠したことが後から発覚した場合などには、遺産分割協議の無効を主張することができます。
遺産分割協議の効力を争う場合には、調停や審判ではなく、地方裁判所に対して「遺産分割協議無効確認」などの民事訴訟を起こす必要があります。
5.遺産分割後に遺言書が発見された場合は?
たとえ遺産分割をした後でも、原則として、遺言者の意思が優先されます。そのため、遺言内容と異なる割合で分割したり、相続人が遺言とは違う遺産を相続した場合などは、その部分は無効となります。
ただし、相続人全員が遺言内容とは異なる分割方法について合意できれば、遺言書を発見する前の遺産分割の効力は有効となります。しかし、相続人のうち一人でも異議を唱えた場合は、遺言内容に従って再分割をする必要があります。
6.まとめ
遺産分割は、家族や親戚など身内の方々と争いになるケースが多く、適当に分割手続きを進めてしまうと、後に大きなトラブルになり、裁判問題に発展してしまうこともあります。
遺産分割で争いになった場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
第三者である弁護士が間に入ることで、遺産分割がスムーズに進み、身内の方々と直接争うストレスからも解放されます。
当事務所は、創業60年の豊富な実績とノウハウを活かし、相続のあらゆるトラブルについて、円満な解決を目指しています。
司法書士の資格を持つ弁護士も在籍しているので、不動産がある相続の場合、登記関係の手続きも含めて、ワンストップでサポートいたします。また、税理士・社会保険労務士とも連携し、相続問題に関わるすべての手続きに対応することが可能です。
相続問題を数多く解決している弁護士だからこそ、争いになる前にそれを予測し、未然に解決策を講じておくこともできます。
初回相談は無料です。弁護士に相談すべきかわからないといった段階からでもお気軽にご相談ください。